こんにちは。じじグラマーのカン太です。
生産管理システムのリニューアル案件を受注できました。製造業のお客様ですが、この機会に原価計算を導入してみたいとのこと。
「かしこまりました!」と二つ返事で回答しましたが、原価計算って全くわかりません。いつも通り勉強しながら開発という綱渡り状態になりそうです。
原価計算の基礎からシステム開発に必要なポイントなどを、何回かに分けてゆっくりまとめていこうと思います。

原価計算とは
原価計算とは、読んで字のごとく製品の原価を計算し、正しく把握することです。
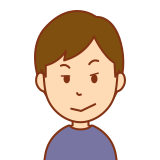
原価なんてだいたいわかってるよ
売値と仕入値がわかってるんだから
町工場のおじさん(偏見ありですね)がよく言うセリフです。毎月同じ製品を毎月同じ量を仕入れて毎月同じ量を出荷している、というような小売り業なら正しいのかもしれません。しかし、実際そんな会社はほとんどありません。
実際の町工場では、いろいろな種類の製品を受注して、それぞれに必要な原材料を仕入れ、それぞれに必要な加工を施し、それぞれの製品に対して検品・梱包・配送などを施しています。
当たり前ですが、そのひとつひとつの工程に対しても経費がかかっています。製品の原価を知るには、その経費がどの製品に対してかかったものなのかを正確に把握する必要があります。
「原価計算」とは、ひとつひとつの製品にかかった経費を算出し、そのひとつひとつの製品が生み出した利益または損失を計算する作業ということになります。
原価計算をするメリット
原価計算をするメリットを考えるには、原価計算をしなければどういうことになるかを考えてみるのがいいかもしれません。
原価計算ができていなければ・・
- 販売部門 ⇒ 製品の価格をきめられない
- 経理部門 ⇒ 財務諸表が作れない
- 製造部門 ⇒ コスト管理ができない
- 経営部門 ⇒ 経営計画がたてられない
ざっと挙げただけでもこれだけのデメリットがあります。
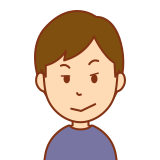
原価計算なんてしなくても、お金の動きは頭に入ってる
そんなものなくても今までちゃんと経営してきた
町工場の経営者の方々はこんな風に思っていることと思います。僕の工場もそうです。
しかし、実際の現場では、製品の単価は他の会社との相場感覚で決定され、年末に大急ぎで経理士に頼んで決算資料を作成し、作業者のコスト意識は皆無で、経営計画なんて考えたこともない・・といった感じになっています。まさにどんぶり勘定のどんぶり経営です。
景気のいい時代や仕事がありあまっている時代であれば、どんぶり勘定でも十分やっていくことができました。長引く構造不況や、AIやデジタル革命による時代の流れの中では、どんぶり経営のままで生き抜くことは難しくなってきています。
原価計算をすることによって、製品単位の原価すなわち利益を知ることができると、自社の強みや弱みを把握できるようになります。そうすることで、限られた経営資源を有効に活用できることにつながります。
原価計算をするメリットは、製造・販売・経営の全てにおいて必要な数字を知ることができることです。
原価計算をするデメリット
原価計算をするメリット、数え上げればきりがないといってもいいほどです。しかし、実際の町工場などで原価計算をきっちりやっているところはほとんどありません。
その最大の理由は、おそらく「めんどうくさい」だと思います。経営者としては、1円の利益も生み出さない(と思い込んでいる)原価の計算などに時間もお金もかけてられない、というところでしょう。また、現場の作業者としては、各製品に対する作業時間の算出なんかに時間をとられたくない、という思いもあるのではないでしょうか。
原価計算をするデメリットは、各担当者の負担が増える(ように思えてしまう)ことにあります。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
中小零細企業、とくに製造業にとって必要な原価計算といったものの概要について考えてみました。人口減が進むこれからの日本では、製造業の未来はそれほど明るくないことは目に見えています。そんな中でも中小零細の製造業が生き残るためには、経営資源の集中が不可欠です。
現時点の自社の経営資源を正確に把握するためにも、小さな会社こそ原価計算を導入する必要があると考えています。
次回は、原価計算の基本中の基本「原価」というものについて考えていこうと思います。



コメント